アイモバイル(6535)は、ふるさと納税サイト「ふるなび」を手がける成長企業でありながら、高い配当利回りも魅力のユニークな銘柄です。
広告事業での収益基盤を持ちつつ、地方創生やデジタルシフトの流れを捉えたビジネス展開にも注目が集まっています。
本記事では、アイモバイルを投資対象として選んだ理由や配当の魅力、事業の将来性とリスク、そして今後の保有方針について、個人投資家目線で詳しく解説します。
選定理由:成長性と高配当を両立

アイモバイルを選定した最大の理由は、成長分野であるふるさと納税を中心とした「ふるなび」事業が順調に拡大しており、今後も需要が続くと見込める点にあります。
加えて、広告代理業という安定的な収益源を背景に、財務的にも堅実な経営をしている点が評価できます。
売上の成長率と利益率を比較しても、規模の割に収益性が高く、ネット系小型株の中でも珍しく、配当還元を積極的に行っている点は特筆すべきでしょう。
規模拡大を図りながらも、株主還元を意識した経営方針が感じられる銘柄であり、バリュー投資の観点からも検討に値します。
ただし、2007年設立、2016年上場と比較的新しめの会社であり、配当を出し始めたのは2021年からなので、配当面での長期安定性はまだ評価できる段階にありません。
配当:利回りの高さと還元姿勢に注目

アイモバイルの配当は、2025年予想で年間26円となっており、株価が約600円台の水準であれば、利回りは4%を超えるやや高めといった水準です。
特に注目すべきは、業績に応じた配当方針をとりつつも、安定・増配を意識していること。
2021年に初配当を出して以降、配当利回りや配当性向は安定していないものの、増配しようとしている努力は見えています。
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 33.33円 | 12.66円 | 13.33円 | 22.00円 | 26.00円 |
営業利益ベースでも十分な余力があり、フリーキャッシュフローも黒字を確保しているため、現時点では無理のない配当といえます。
事業

将来性:ふるさと納税市場の拡大が追い風
ふるさと納税ポータルサイト「ふるなび」は、自治体とユーザーを結ぶサービスとして着実に成長しており、今や同社の主力事業となっています。
ふるさと納税市場は年々拡大傾向にあり、毎年のように寄付総額が増えています。
制度の安定性も確認されているため、中長期的に高いニーズが見込まれます。
加えて、自治体向けのDX支援や返礼品管理の最適化など、ソリューション提供型のサービス展開も行っており、単なる仲介からコンサル・システム開発への進化が期待されます。
デジタル行政支援という文脈でも成長性があり、今後も公共×IT分野の需要を取り込める可能性が高いと見ています。
懸念点:制度変更リスクと事業依存度の高さ
懸念点としては、やはり「ふるさと納税制度」自体の制度リスクが挙げられます。
例えば、返礼品の規制強化や制度変更が実施されると、サイト利用者数の減少や取扱高の落ち込みにつながる可能性があります。
実際、2025年10月1日からふるさと納税のポイント付与が廃止になるため、2026年からのふるさと納税がどの程度の寄付額になるかは不透明です。
また、現在の収益の大部分を「ふるなび」事業に依存している構造であるため、事業の多角化が課題となるでしょう。
広告代理業も競争が激しく、粗利率が下がる懸念もある中で、将来的な新規事業の柱づくりがどれだけ進むかが、株価の持続的成長において重要な鍵を握ります。
今後の保有方針:高配当維持を前提に継続保有
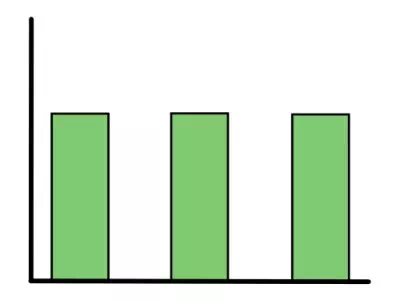
アイモバイルは、現時点で「高配当狙いの分散投資先」としてポートフォリオに組み込んでいます。
配当利回りの高さに加え、事業の成長余地と収益性を評価していますが、制度変更リスクを踏まえ、全体の一部にとどめる方針です。
今後、ふるさと納税の制度安定が見込まれる場合には、買い増しも検討したいと思っています。
また、中長期的に広告事業の伸長や新規事業の育成が見えれば、再評価のタイミングが来る可能性もあるため、決算チェックは引き続き継続します。
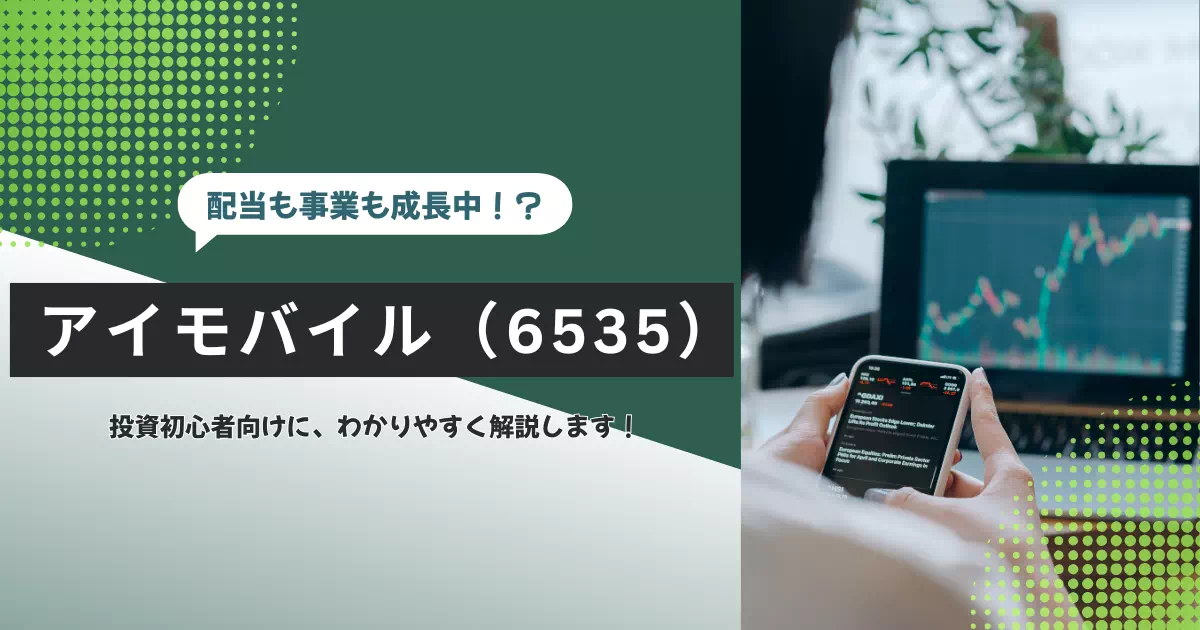
コメント