2025年2月から開始した投資信託積み立て記録です。
・SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
・三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
を1万円/月ずつ積み立てています!
2025年09月結果
| ファンド(愛称) | 区分 | 保有口数 | 取得単価 | 取得金額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| サクっと純金(※1) | 特定預り | 46,166口 | 17,329円 | 80,001円 | +13,660円 |
| S&P500(※2) | NISA つみたて投資枠 | 24,677口 | 32,419円 | 80,000円 | +9,232円 |
※1 SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
※2 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
所感

今月も引き続き日本株やS&P500など、各相場が全体的に上昇傾向だったこともあってか、どちらのファンドも評価損益は先月から上昇となりました。
特に金相場は9月末に上昇し続けて高値更新のニュースが目立つようになりました。
その分、取得単価が高まってしまいました。
これは積み立て投資型では仕方ないことですね。
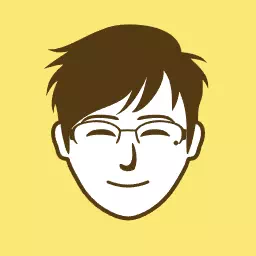 クルエイチ
クルエイチ投資信託を開始して約半年が経ちました。
長期投資ものなので1ヶ月単位で一喜一憂するものではないですが、やはり損益がプラスなのは嬉しいですね!
サクっと純金


2025年9月末、ゴールド(金)を投資対象とする投資信託は大幅に基準価額が上昇し、多くの投資家の注目を集めました。
この短期間での急騰は単一の理由ではなく、世界経済や地政学的な複数の要因が複雑に絡み合った結果のようです。(※Geminiによる要約)
金価格の上昇を語る上で、最も大きなドライバーとなったのは、米国の金融政策の方向転換への期待と、それによる米ドル(USD)の動向です。
- 米FRBによる利下げ観測の強まり
-
米国の中央銀行であるFRB(連邦準備制度理事会)が、利下げサイクルに入るという観測が9月に入り一層強まりました。
政策金利が引き下げられると、利息を生み出さない金への投資の相対的な魅力が増します。
債券などの利回り低下を嫌った資金が、「究極の安全資産」である金へとシフトしたことが、価格上昇の大きな要因です。 - ドル安の進行と金の割安感
-
金は国際的に米ドル建てで取引されます。利下げ観測は米ドルの価値を下げる(ドル安)傾向にあり、ドル安が進行すると、ドル以外の通貨を持つ投資家から見れば金が割安に見えます。これにより、世界的な金への需要が一気に高まりました。
金融政策の要因に加え、世界各地の緊張の高まりや、各国中央銀行の動きも、金を歴史的な高値圏へと押し上げました。
- 絶え間ない国際紛争と安全資産への避難
-
ロシア・ウクライナ紛争の長期化に加え、中東情勢の緊張(特にイランへの国連制裁復活の動き)や、ウクライナ軍による攻撃の激化など、9月後半にかけて地政学的リスクが一段と高まりました。
このような不確実性の高い状況下では、株式やその他のリスク資産から資金が引き揚げられ、信頼性の高い金への避難的な需要が集中します。 - 各国中央銀行による戦略的な「金買い」
-
近年注目すべきは、各国の中央銀行の動きです。
自国通貨や米ドルへの依存度を下げるため、特に中国をはじめとする新興国の中央銀行が外貨準備として金を大量に購入し続けています。
この戦略的な買い付けは、市場全体の供給量を減らし、金の構造的な需要を押し上げる要因となっています。 - インフレヘッジとしての機能
-
世界的な物価高(インフレ)が続く中で、紙幣(法定通貨)の価値が実質的に目減りするリスクが高まっています。
金は政府の信用に依存しない実物資産であるため、資産の目減りを防ぐインフレヘッジとしても強く求められ、需要の底上げに貢献しています。
上記の国際的な要因に加え、日本の投資信託(円建て)の基準価額を大きく押し上げたのは、国内特有の為替要因です。
金価格は国際市場でドル建てで決まりますが、これを日本国内で円に換算する際、円安であればあるほど円建ての価格は上昇します。
国際的な金価格の上昇という「追い風」に、歴史的な円安基調という「さらなる追い風」が加わることで、日本の投資信託の基準価額は大幅な上昇を記録しました。
S&P500


2025年9月末、米国株式市場の主要指数であるS&P500指数もまた、ゴールドほどではありませんが堅調に上昇しました。
これは、世界的な「リスク回避」のムードが強かった金相場とは対照的に、景気の先行きに対する楽観的な見方と、リスクオンの動きが優勢になったことを示しています。(※Geminiによる要約)
S&P500の上昇を牽引した主要なドライバーは、米国の金融政策、特にFRB(連邦準備制度理事会)が金融緩和へと舵を切るという市場の強い期待です。
- FRBの利下げ観測が景気下支えの期待に
-
9月のFOMC(連邦公開市場委員会)で、利下げが実施された、あるいは利下げサイクルが間近に迫っているという観測が高まりました。
金利の低下は、企業や個人の経済活動にとって非常に大きなプラス材料となります。- 企業コストの削減:借入コストが下がることで、企業の設備投資や研究開発への意欲が高まります。
- 消費の刺激:住宅ローンや自動車ローンなどの金利負担が減り、個人消費(米国経済の約7割を占める)が活性化するという見通しが、企業業績への期待を高めました。
- 株式の理論的な価値向上
-
金利の低下は、株式が将来生み出すキャッシュフローの現在価値を押し上げることになるため、株価の理論的な割安感を生み出します。
市場はこの理論的な裏付けと、景気回復への期待を織り込み、積極的に株を買い進めました。
マクロ経済的な期待に加え、S&P500を構成する企業のパフォーマンス自体も、株価の上昇を支える重要な土台となりました。
- ハイテク銘柄主導の力強い上昇
-
S&P500指数の中でも、特に情報技術セクターやAI関連企業など、成長性の高いハイテク銘柄が引き続き市場の上昇を牽引しました。
これらの企業は、不透明な経済状況の中でも高い収益力を維持しており、その好業績が指数全体を押し上げました。
9月末の動きを見ても、セクター別では「情報技術」などが特に好調でした。 - 粘り強い企業活動がアノマリーを打破
-
9月は歴史的にS&P500が年間で最も下落しやすい月とされる「9月アノマリー(経験則)」が存在します。
しかし、2025年9月は、利下げ期待という大きな追い風と、企業活動の底堅さがこのネガティブなアノマリーを打ち消す形となりました。 - 一時的なリスク要因の克服
-
月末にかけて、米連邦政府機関の一部閉鎖リスクなど、市場の重荷となり得る政治的なニュースも一部で報じられました。
しかし、S&P500は一時的に値を下げる場面があったものの、最終的にはこれを乗り越えて底堅い推移を維持し、投資家の景気に対する自信が勝った形となりました。

コメント