「損益計算書」について解説します。
企業の経営成績を読み解くうえで欠かせないのが損益計算書(P/L)です。
売上や費用、利益の構造を理解することで、その企業がどれだけ効率よく収益を上げているかが見えてきます。
この記事では、損益計算書の基本構造と各項目の意味、貸借対照表との違い、分析のポイント、さらには実際の企業分析への活かし方までを丁寧に解説。
投資判断に役立つ“読み方”と“使い方”を初心者にもわかりやすく紹介します。
損益計算書(P/L)とは?
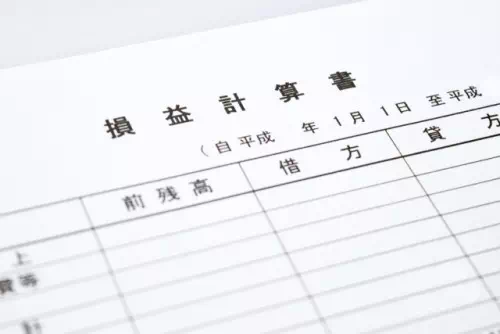
損益計算書の定義と目的
損益計算書とは、企業がある一定期間(1年、四半期)における収益と費用をまとめた財務書類で、一定期間の企業の経営成績を明らかにする報告書です。
売上から順に、売上原価、販管費、営業利益、経常利益、そして当期純利益までの流れが一目で分かるようになっています。
株式投資においては、この損益計算書を読むことで、その企業が儲かっているのか、利益が安定しているのか、成長しているのかを判断する重要な材料となります。
特に初心者は「どのくらい稼いで、どれくらい残っているのか」を知る第一歩として活用できます。
貸借対照表との違い
損益計算書と貸借対照表は、企業の財務状況を知るための重要な書類ですが、それぞれ役割が異なります。
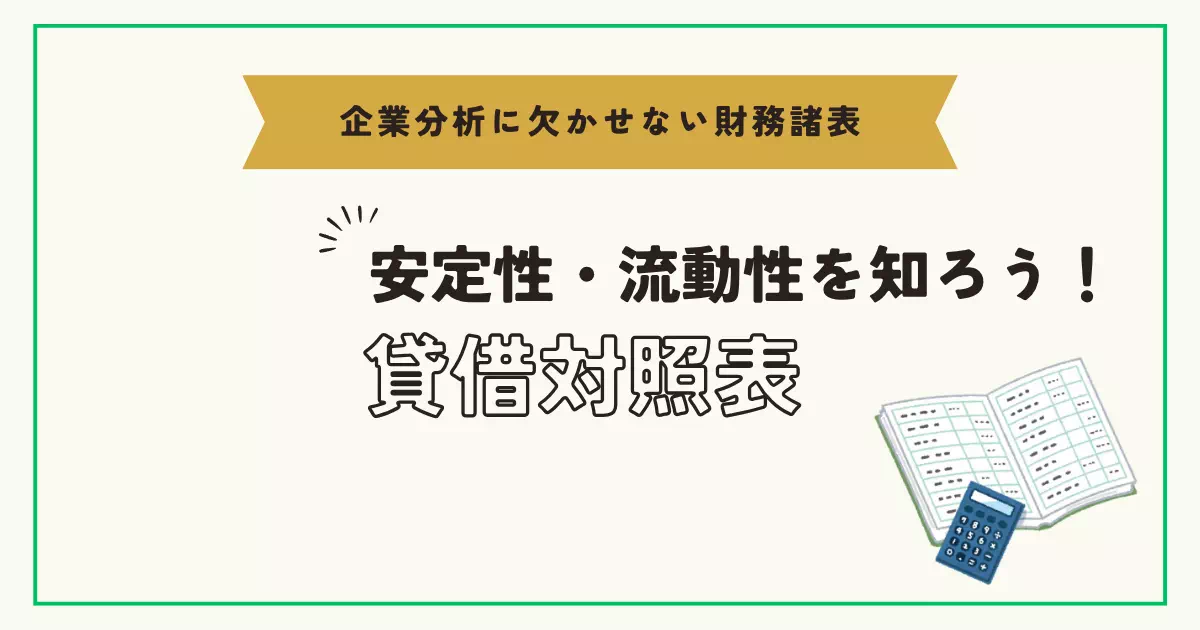
損益計算書は「期間中の経営成績」を示し、売上や費用、利益の流れを把握するためのものです。
一方、貸借対照表は「ある時点での財政状態」を表しており、企業がどのような資産を持ち、どのような負債や資本で成り立っているのかを示します。
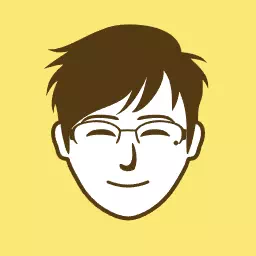 クルエイチ
クルエイチ損益計算書は“企業の稼ぐ力”
貸借対照表は“企業の持ち物と借金のバランス”
を表す!
英語表記と国際的な呼称
損益計算書は、英語では「Profit and Loss Statement」または「P/L(ピーエル)」と呼ばれます。
海外の投資家やグローバル企業ではこの呼称が一般的で、財務諸表の中でも基本的な書類のひとつです。
また、「Income Statement」という表現も使われることがあります。
どれも企業の収益や費用、最終的な利益を示す書類を指しており、国際的な企業分析では英語表記に慣れておくと、海外銘柄の情報収集や比較にも役立ちます。
損益計算書の構造


損益計算書の構造は、企業の収益と費用の流れを上から順にたどる形になっています。
最初に記載されるのが「売上高」で、これはその期間中に企業が商品やサービスを販売して得た総収入を表します。
次に「売上原価」が続き、売上を得るために直接かかった費用、たとえば材料費や仕入れコストなどが含まれます。
売上高から売上原価を引いたものが「売上総利益」で、企業の粗利とも呼ばれます。
| 損益計算書 項目 | 計算例 |
|---|---|
| 売上高 | 10,000円 |
| 売上原価(仕入) | 4,000円 |
| 売上総利益(粗利) | 10,000 – 4,000 = 6,000円 |
続いて、「販売費および一般管理費(販管費)」が記載されます。
これは、販売活動や管理業務にかかった間接的な費用で、広告宣伝費、人件費、オフィスの賃料などが該当します。
売上総利益から販管費を引いたものが「営業利益」となり、本業による利益の実力を示す重要な指標です。
| 損益計算書 項目 | 計算例 |
|---|---|
| 売上総利益 | 6,000円 |
| 販売費および一般管理費(販管費) | 3,000円 |
| 営業利益 | 6,000 – 3,000 = 3,000円 |
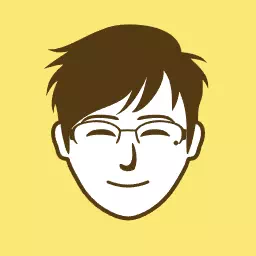
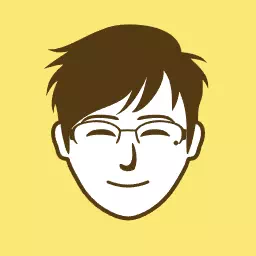
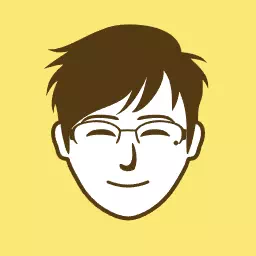
営業利益は本業の儲けを表します
さらに、「営業外収益」や「営業外費用」といった本業以外の損益が加味されて「経常利益」が求められます。
「営業外収益」には受取利息や受取配当金、「営業外費用」には支払利息などが含まれます。
| 損益計算書 項目 | 計算例 |
|---|---|
| 営業利益 | 3,000円 |
| 営業外収益 | 2,000円 |
| 営業外費用 | 1,000円 |
| 経常利益 | 3,000 + 2,000 – 1,000 = 4,000円 |
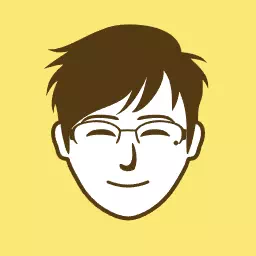
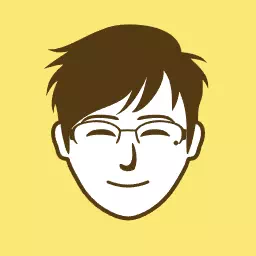
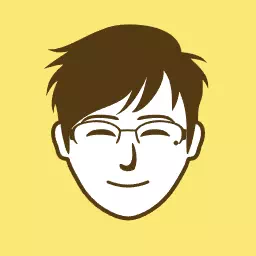
経常利益は本業だけでなく財務活動なども含めた、会社トータルの業績を表します
その後、「特別利益」「特別損失」など一時的な要因(不動産売買損益など)による損益を経て、「税引前当期純利益」が表示されます。
そこから法人税等を差し引いたものが「当期純利益」です。
| 損益計算書 項目 | 計算例 |
|---|---|
| 経常利益 | 4,000円 |
| 特別利益 | 3,000円 |
| 特別損失 | 1,000円 |
| ┗税引前当期純利益 | 4,000 + 3,000 – 1,000 = 6,000円 |
| ┗法人税、住民税、事業税 | 3,000円 |
| 当期純利益 | 6,000 – 3,000 = 3,000円 |
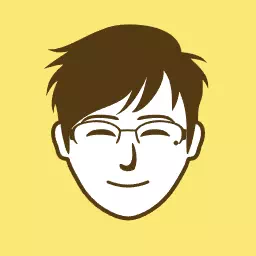
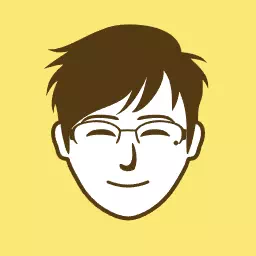
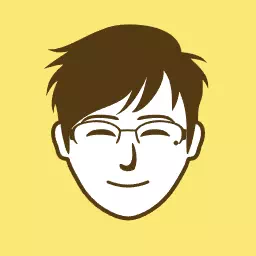
当期純利益は最終的に企業が得た純粋な利益を表します
損益計算書の読み方:投資判断に活かすポイント
利益の推移と安定性の確認
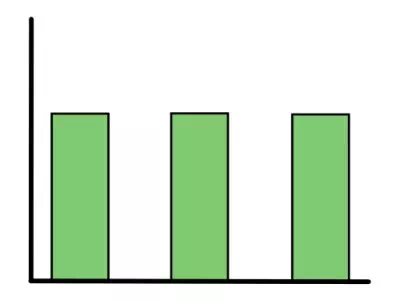
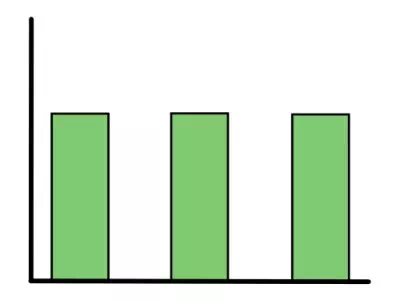
企業の利益が年ごとにどのように推移しているかを見ることは、安定した経営ができているかを判断するうえで重要です。
毎年安定して利益を出している企業は、外部環境の変化にも強く、長期投資に向いています。
逆に、利益が大きく上下している場合は、業績が景気や一時的要因に左右されやすく、リスクが高まる可能性があります。
収益性指標の分析
損益計算書では、企業の収益性を判断するために「売上総利益率」や「営業利益率」などの指標が使われます。
売上総利益率は、売上に対してどれだけの利益が残ったかを示し、原価の管理力を表します。
一方、営業利益率は本業からどれほどの利益を生み出せたかを示す重要な指標で、競争力やコスト効率を分析するのに役立ちます。
費用構造の変化とその影響


費用構造の変化を見ることで、企業がどのように経営資源を使っているかが分かります。
例えば、人件費や広告費が急増している場合は、成長投資かコスト増かを見極める必要があります。
また、売上に対して販管費が増加している場合、効率が悪化している可能性もあります。
費用の増減は利益に直結するため、注意深く確認することが重要です。
特別損益の頻度と内容のチェック


特別利益や特別損失は、通常の営業活動とは直接関係のない一時的な収益や費用を指します。
例えば、不動産の売却益や自然災害による損失などが該当します。
これらは企業の本来の収益力を反映しないため、頻繁に発生している場合は注意が必要です。
特別損益が多い企業は、安定した利益を出す力が弱い可能性があります。
他の財務諸表との連携による総合的な評価
損益計算書だけでなく、貸借対照表(B/S)やキャッシュフロー計算書(C/F)と合わせて読むことで、企業の全体像が見えてきます。
例えば、利益が出ていてもキャッシュが不足している場合、資金繰りに問題があるかもしれません。
B/Sからは財務体質、C/Fからは現金の流れを確認でき、損益計算書の数値をより正確に評価することができます。
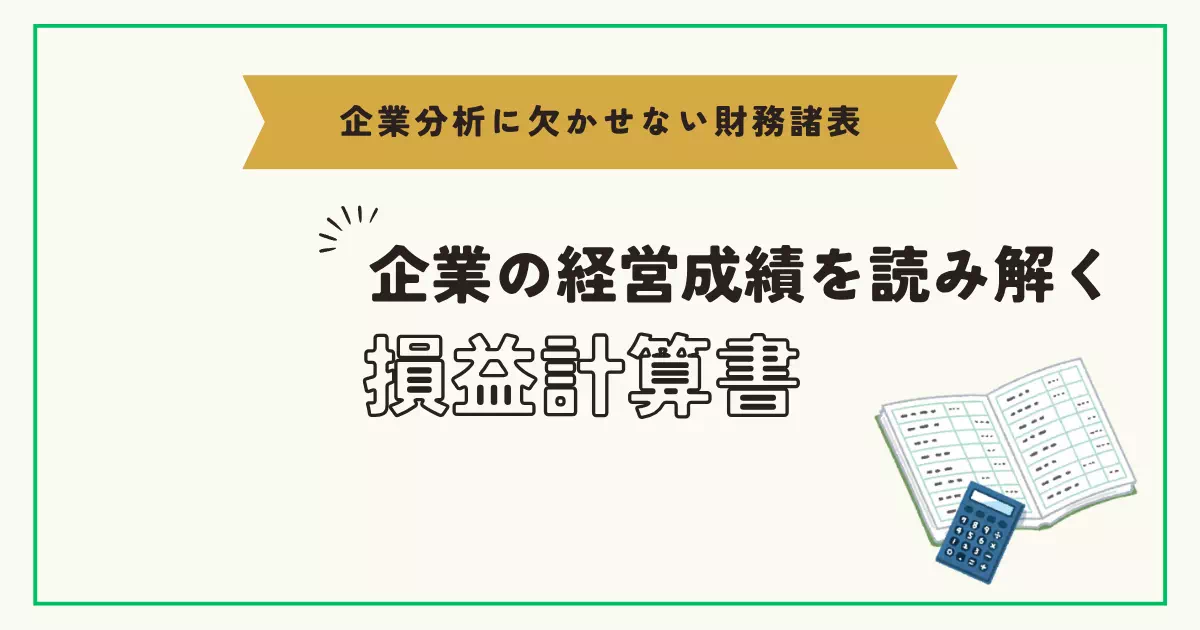
コメント